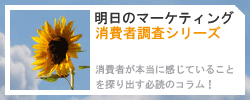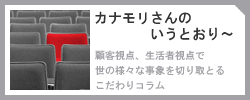ウォルマートのような米国小売業のオムニチャネル戦略を歴史的にふりかえってみると・・・といっても、この10年くらいの短い歴史だが・・・、最初のころに比べると、その中身が変化してきていることがわかる。
第1段階は2000年代半ばで、O2O(Online To Offline)、つまりオンラインからオフラインへといわれていたころ。ウォルマートでいえば、2005年からの2年間のテストをへて、2007年にネットで注文した商品を店舗で受け取れるサービスを全店で始めたころだ。ウォルマートのテストによれば、ネットで注文した客の3分の1が店舗で受け取ることを選択する。そして、そういった客の60%が店舗に来たついでに60ドルの付加購買(衝動買い+ついで買い)をする。
だから、店舗受取りサービスを提供することで付加売上が期待できるリアル店舗のほうが、アマゾンのようなネット専業よりも競争優位にたてる・・・というのが当時の評価だった。
アマゾンが、年会費79ドル払うプライム会員に、無料で2日以内に配送というサービスを始めたのは2005年1月。それまでは25ドル以上注文の場合は配送料無料・・・というよくある常識的サービスを提供していた。無料配送サービスは期待以上の効果を発揮し、プライム会員は通常顧客よりも150%も多く購買し、よって、会員になってから(サービス開始前に予測した)2年ではなく、3か月で損益分岐に達することが明らかになったという(現在では、プライム会員の平均購買金額は通常顧客の2倍だといわれる)。
こういったアマゾンに対する対抗策として小売店も自社サイトで無料で迅速な配送サービスを進めざるをえなくなったわけだ。が、なにせ経費がかかる。それだったら客に店に受け取りにきてもらおう。これが、O2Oが始まった理由だといわれる。
(店舗受取りサービスが始まった理由が店舗側の経済的理由であったとしても、一言つけ加えておきたいことがある。米国における店舗受取サービスは、日本で考える以上に、消費者にとって便利なサービスだということ。日本の宅配便サービスと違って、米国では細かい時間帯指定はできないし、不在の場合、電話したらすぐに指定した時間帯に再配達してくれるなんてこともない。再配達も2・3回くらいはしてくれるようだが、いずれも運悪く不在だった場合は、自ら配送センターまで取りにいくはめになる。だから、、自分に都合のよい時間に、自分が選択した店舗に受け取りにいくほうがよほど便利・・・ということになる)。
2005年からプライム会員に無料で迅速な配送を始めたアマゾンは、毎年平均34%という驚異の売上成長をつづけていくが、営業利益率は2004年の6%をピークにして、その後は下がり続け、2011年には2%にまで落ち込んだ。小売業の利益率は米国でも低いが、それでもウォルマートは6%くらいを維持している。アマゾンの場合、売上高の9%くらいだといわれる配送経費と物流センター構築への投資が負担になっているのだ。つまり、無料配送と迅速な配送は、売上増には大きく寄与していても、経費は確実にかかり、アマゾンの利益を圧迫しているわけだ。
(ZOZOTOWNを運営しているスタートトゥデイの社長が「配送するにはそれだけ金がかかるのだ」と無料配送を支持する客を叱咤して炎上した事件があったが、怒る気持ちはよくわかる。アマゾンが無料サービスを提供しながら利益も出しているのならともかくも、利益もださずに無料配送をつづける会社のまねをするなんて・・・・と言いたくもなる。もっとも、アマゾンを創立する前にウォールストリートで働いていたベソスCEOは数字に強く、利益よりもキャッシュフローのほうが重要なんだと投資家たちに説いているくらいだ。その言葉どおり、アマゾンは営業利益は少なくても現金は常に潤沢に保有している)。
米国大規模小売業は、その後も、リアル店舗の強みをいかすために、スマホやタブレットといったモバイル端末の利用をすすめ、店舗の発信力を高めていった。これが第2段階だ。たとえば、(こういったことは日本の小売業でもやっていることだが)、スマホにアプリをダウンロードした客は、自分がいま現在いる場所から一番近い店に欲しい商品があるかどうか調べ、在庫を確認してからその店を訪れることができる。事前に店内のレイアウトがチェックでき、その商品がどこにあるか棚の位置さえも調べることもできる。
まあ、こういったサービスは消費者にとっては、それほど魅力あるものでもない。だが、次のようなサービスは大切だろう。
たとえば、目当ての商品を実際に手に取ってみたら色が気に入らなかった、あるいはサイズが合わなかった。そんなときには、店員がタブレット端末で、あるいは客が店内設置の端末で、色違いやサイズ違いの在庫が他店舗にあるかどうかを調べ、場合によって、取り寄せてもらう、あるいは、直接自宅に配送してもらうなどの選択ができる。
こういったことを可能にするためには、在庫情報、つまりリアルタイムに更新される一元化された在庫データベースが存在しなくてはいけない。こういった在庫データベースを構築した小売店は店舗のネットワーク化を進めることにより、アマゾンと、少なくとも互角に戦えるプラットフォームをもつことになる
そして、ここで、オムニチャネル戦略の第3段階にはいる。
ラストマイルの戦いとかラストマイルの問題とかいった用語を最近よく耳にする。もともとは電話などの有線通信サービス業で使われた言葉だ。幹線を構築するのはよいとして、問題は(つまり、一番経費がかかるのは)、たとえば、電話局(加入者局)から各家庭に線を引っ張るところにある・・・という意味で、最後の1マイル問題といわれた。ネット通販では、物流センターまではよいとして、そこから各顧客の自宅まで個別に荷物を配送するロジスティクスの問題が一番悩ましい。いかにして、あまり経費をかけずに、しかも、早く届けられるか?
いま、ネット専業のアマゾンと大規模小売業とは、このラスト1マイルをめぐって戦いをくりひろげている。宣伝上手なアマゾンは、無線操縦する模型ヘリコプターのような「ドローン」を飛ばして、近いうちに・・・米連邦航空局の許可がおりれば2015年ごろには、物流センターから30分以内に顧客宅に配送するとPRしている。あるいは、都市部ではバイクをつかって有料で一時間以内の配送、プライム会員なら無料の2時間配送テストも開始している。
その一方で、大規模小売店はリアル店舗をつかってラストマイルの問題を解決しようとしている。Ship from Store(店舗からの出荷)だ。
たとえば、ウォルマートなら、顧客Aさんが商品をウォルマートサイトで注文したとして、早く届けるためにはいくつかの選択肢がある。Aさんの自宅がどこにあるかで、物流センターが近ければそこから業者をつかって直接配送する。だが、Aさんの自宅に近いところにX店舗があるとしよう。そのX店舗に在庫があればその日のうちに届けられる。だが、あいにくX店舗に該当商品の在庫がない。次に考えられるのが、X店舗に一番近いY店舗で、ここに在庫がある。①Y店舗からX店舗に届けて、X店舗から自宅配送(あるいは店舗受取り)。②Y店舗から直接配送、③物流センターから配送。この3つの選択肢のなかから、どれが経費が安いか、そして、どれが一番早く顧客のAさんちにとどけられるかという2つの条件を考えてベストな選択をする。コンピュータが最適化分析をして、1つの選択肢を指示してくれる。
Ship from Store(店舗から出荷)戦略においては、アマゾンの米国内で60以上ある物流センターと、たとえばウォルマートなら4400店舗、メイシーグループなら・メイシーやブルーミングデール百貨店で850店舗を物流拠点として、どっちがコストとスピードで優位にたつかということだ。
現在、ウォルマートの83件の大型店舗スーパーセンターでは、ウォルマートサイトで注文された商品の5分の1を出荷しているそうだ。これに、店舗に受け取りに来る客を含めると、ネット注文の半分は、店舗受取か店舗出荷ということになるようだ。
一元化された商品在庫データベースと最適化分析をしてくれるソフトウェアプログラムとが、注文がオンライン、店舗、コールセンター、カタログ・・・と、どのチャネルからであろうとも、リアルタイム在庫、場所、注文状況を提供してくれる。在庫、物流コスト、人件費やサービスレベルなどを考慮して、どこから出荷すべきか決定してくれる。ウォルマートはこういったデータベース・プラットフォームを構築するのに4億3000万ドル投資したという。
物流拠点としてのリアル店舗をネットワーク化をすることで、ネット専業アマゾンに、物流コストと配送速度で対抗しようというわけだ。が、このアマゾンとの競争において、リアルタイム在庫データベースの構築を進めている大規模小売業は、結果として、小売業の3大ロス(損失)といわれる値引きによるロス、廃棄によるロス、そして販売機会ロスの減少を実現することになる。危機感がなければ、これほど厖大な努力や投資はできない。アマゾンの脅威が米国小売業のムダを排除し利益の向上を生むわけだ。
オムニチャネルの本質は、店舗小売業が一元化されたリアルタイム在庫のデータベースをもつようになることにある。これは、小売業の利益を向上することに直接つながり、長年の小売り業の悩みをかなりのレベルで解決してくれる。ネット専業と競争するなかで、店舗小売業の財務体質は頑強なものになっていくはずだ。
考えてみれば、アマゾンが日本に進出した2000年、書店は全国で23000店舗ほどあった。この書店と取次店が協力して在庫のリアルタイム一元化をはかり、朝注文したら夕方には店舗で受け取れるというシステムを構築していたら、書店数が14年間で10000店近く減ることはなかっただろう (もっとも、タブレット端末も存在していなかった当時のIT環境では、無理だったと考えるのが妥当かもしれない)。
話は突然変わるが、アマゾンは配送料無料サービスをずっと維持していくことができるのだろうか?
アマゾンが利益も出さないのに積極投資を続けることができたのは株価が高かった。つまり、投資家たちがアマゾンの将来性を信じてついてきたことにある。「アマゾンは消費者利益のために投資家たちによって支えらえている慈善団体だ」と揶揄したアナリストもいるくらいだ。だが、さずがの投資家たちも20年間これといった利益が出ないのにはうんざりしてきたらしく、2014年に入ったころから株価も下がる傾向がみられ、さずがにこのままではいけないと思ったのだろう。アマゾンも利益を上げる意志をみせるために、2005年開始以来初めて、プライム会員費を79ドルから99ドルへと値上げした。
その後、会費の値上げにもかかわらずプライム会員数が増大したということで、(数字を公表しないアマゾンだが、世界市場で53%増加したといわれる)、下がった株価はまた上がった。だが、これは本当にグッドニュースなのだろうか?
FacebookやGoogleが無料サービスを広告収入で支えているように、サービスにかかる経費による損失は、どこかで埋め合わされなくてはいけない。購買客の45%を占めるというプライム会員の年間購買金額が非会員客の2倍だとしても、それで配送経費や物流センターへの投資をカバーすることは無理だろう。
FacebookやGoogleはアクセス客が増えても、それに合わせてサービス提供費用が相関関係的に増えるわけではない。しかし、アマゾンの配送経費は、プライム会員がふえればふえるほど相関関係的に増える。どこまでいっても、いたちごっこだ。いくらクラウドコンピューティングサービスや広告といった他の収入が成長しているといっても、アマゾンの無料ビジネスモデルで大幅に利益が増大する可能性はあるのだろうか?
そもそも、90年代後半にネット関連サービス企業が登場するとともに無料が当然のような風潮になってはいるが、この風潮は10年後もつづいているだろうか? 言葉を変えていえば、無料のビジネスモデルは10年後も存続しているだろうか? 欧州では、フランスのようにアマゾンの無料配送を法律で禁止した国もある。また、Google やFacebookのように個人データにもとづいて広告収入をあげるビジネスモデルへの反対も根強くある。
わたし的には、10年後に配送料無料サービスがなくなっていたとしても驚かない。誰もがそうしたくないのに、アマゾンという企業一社にひっぱられてやっているだけなのだから。そのアマゾンが、今後10年間も、これまでの20年間と同じように利益を出さずに投資家を魅了しつづけていられるとは思わない。株価が下がれば、アマゾンだって配送料を有料化せざるをえないだろう。それに、消費者も、タダでサービスが受けられるのに慣れてしまうことはよくないことだと思う。タダより高いものはない。結局、どこかで支払っているのだから。どこで支払っているのかが明確になっていたほうがいい。(・・・・などと評論家ぶっておえらいことをいいながら、ほとんど毎日、アマゾンで買ってまーす。だって、ペットフード一個買うだけでも配送料無料なんだもの。この便利さ、一度慣れたらやめられなーい~)。
参考文献:1. David Streitfeld, Amazon Reports a Profit, Citing Prime as the Key, The New York Times, 1/29/2015, Austin Carr, The Real Story Behind Jeff Bezos’s Fire Phone Debacle And What It Means For Amazon’s Future, Fast Company , 1/6/2015, 3. Shelly Banjo, Can Wal-Mart Clerks Ship as Fast as Amazon Robots?, The Wall Street Journal, 12/18/2014, 4.Steve Banker Amazon vs. Walmart: E-Commerce vs. Omni-channel Logistics, Forbes, 10/4/2013
Copyrights 2015 by Kazuko Rudy. All rights reserved.