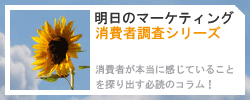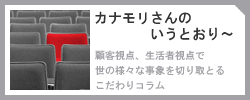東京オリンピック招致が成功して以来、「おもてなし」が手ぶりつきで流行している。滝川クリステルがした手ぶりだからチャーミングだったが、猪瀬都知事がしていたらギャグ漫画だ。
あれ以来、滝川クリステルはすっかりCMの人気者になった。そして、「おもてなし」の定義とか語原とかも熱く論じられるようになっている。接客マナーを教える人は、「表裏なし」という語原を強調し、表裏のない気持ち、真心をもって客を迎えることだと説明する。が、これは、かなり後世になっての意味づけだ。客商売をする人たちが、「商い(あきない)」=「飽きない」とゴロ合わせをして、商売は飽きずに辛抱強くつづけるものと言い伝えたのに似ている。
実際には、国語国文学の専門家が説くように、「おもてなし」は、「もてなす」という動詞が名詞化された「もてなし」に丁寧語の「お」がついたもの。そして、「もてなす」という言葉は、「そのように扱う」とか「そのようにする」といった意味の「成す」に、その動詞を強調する「もて」という接頭語がついたもの。本来は、「とりなす」とか「取り扱う」「待遇する」といった意味でつかわれ、接待するような意味合いでつかわれるようになったのは中世以降になってからだそうだ。
いずれにしても、「おもてなし」はあくまで受け身の言葉である。つまり、店にやってきた客、旅館やホテルにやってきた客を「そのように扱う」、この場合、「VIP客であるかのように扱う」ということになる。
日本人が大好きなピーター・ドラッカーは、著書「マネジメント:務め、責任、実践」で、世界で最初に近代的マーケティングを実行したのは、17世紀半ばの日本の「越後屋」だと書いている。いまの日本橋三越の前身である越後屋が、江戸時代に、世界にさきがけて、革新的マーケティングを始めたというのだ。それまでは、商売は自分がつくったものを売ることだった。が、越後屋は京都をはじめ日本各地からさまざまな呉服物を仕入れて顧客に提供した。しかも、現金で買う客は、武士であろうと町民であろうと正札の値段どおりに販売した。現在の価値で年商100億円の売上をあげ、店員(小僧)は300人以上。規模からいっても世界最初の大型量販店だったといわれる。
この越後屋時代の接客精神を、1904年(明治37年)に日本最初の百貨店といわれる株式会社三越呉服店が設立してからも受け継ごうということで、1907年(明治40年)につくられたのが「三越小僧読本」。小僧、つまり店員に配られた書には、商人道とそれを実践する店員の接客心得が10か条にまとめられている。
「お客様は神様」という考え方の源となっているような箇所もみられる・・・・「そもそもお客本位といふは、御客様大明神のことなり、お客様一大事なり、御客様の御無理を御道理とするにあるなり」と書いてある。
これが、日本の接客精神「おもてなし」の基本だ。
小僧読本には次のような箇所もある。現代語に訳すと「お客様は子供のようなものだと思え。三越の小僧はその相手だと思えば間違いがない。だから、どんな無理難題も受け流して、店内にいる限りは、楽しく愉快に過ごしてもらうことが大切。入店の時には、家庭に不幸、悩み、怒り、不機嫌などがあろうとも、店を出るときには『ああ、気持ちがさっぱりした。三越で遊んだので心の底まで愉快になった』と思っていただくようになれば、三越の繁栄は今日とはくらべものもないほどの高みを達成するはずだ。・・・・だから、三越の小僧は、一瞬間とも油断せず、いちいちお客様の脈を取らぬまでに、親切、用意、慇懃、正直、機敏、あらゆるさじ加減をもちいるべきである」
まさに、これが、いまの日本の接客業における「おもてなし」の精神の基本である。店内にいる間は、すべての不快感を忘れて(というか、それを小僧にぶつけることで忘れて)、さっぱりした快の気分で出て行っていただく。
ここには、顧客セグメンテーションとか顧客戦略などというものは厳密には存在しない。来る者はこばまず。来店あたり10万円つかう上客であろうと1000円しかつかわない客であろうと差別なく、「お客様はみな神さま」。店舗という販売形態においては、1日の来店客数が100人だろうと1000人だろうと、人件費を含めた固定費に変わりない。店を1日開けているのに必要な経費が、客の数に関係なく同じであれば、1000円でも多く売上があったほうがよい。来店客はその質よりも量が重要になる。
気配りするのに余分の経費がかかるわけではない。だから、お客様は差別なく、むずがって駄々をこねる子供だと思ってもてなす。
お客様は平等に神様として待遇される。
客を差別しないのなら顧客戦略は必要ない。
顧客戦略が必要になるのは、売り手側から買い手側である客にコミュニケーションをしかけるとき。つまり、受け身ではなく、売り手から能動的に客に働きかけるときだ。TVや新聞、雑誌といったマス媒体を通じて広告メッセージを送るときにも、ターゲットとなる顧客セグメントを決め、それに合わせたメッセージ内容やデザインにするといったクリエイティブを考える。おおざっぱな顧客戦略は必要だ。だが、歴史的にみて、顧客戦略を発展させたのは通信販売を含めたダイレクトマーケティング企業だろう。
顧客セグメントに合わせて営業部員が訪問する(銀行や保険なら外交員、デパートなら外商にあたる)、あるいは、ダイレクトメール(カタログ)を送ったり、電話をしたり、eメールを送る。要は、顧客がもたらしてくれる利益に合わせて、つかうチャネルやコミュニケーション内容(コンテンツ)を変える。それによって、投資利益率の最適化をはかる。ダイレクトマーケティング企業が精通しているのは、顧客をその現在や将来の利益性によってセグメンテーションし、それに見合った投資をするという顧客戦略だ。
こういったデータに基づく顧客戦略は、競争市場がネットに移行することで必要なくなった。ネット販売におけるダイレクトマーケティングでは、顧客戦略は必要ない。
ネットは、古い販売形態である店舗販売と同じように受け身のチャネルだ。アクセスしてくる客に対応するネット販売は、店舗販売以上に顧客戦略を必要としない。ネット上での「おもてなし」はデータに基づく。過去データやリアルタイムのアクセスログデータに基づいて、アクセス客一人一人にパーソナライズされたメッセージを提示する。こういったことを実現するために初期のシステム投資はかかっても、パーソナライズされた「おもてなし」を100万人に提供しようとも1000万人に提供しようとも付加経費は発生しない。店舗と同じように、アクセスしてきた客が1000円購買してくれる客か10万円購買してくれる客かには無関係に、誰にも平等なサービスを提供することができる。店舗では、一人一人にパーソナライズなサービスを提供するにはより多くの数の店員を配置しなくてはいけない場合もある。が、オンライン上では、すべての客は(店舗販売以上に)公平かつ平等に「おもてなし」を享受することができる。
だから、オンライン上では、顧客戦略はいらない。戦略などなくても、つまり、投資利益率を考えることなく、一人一人にパーソナルなサービスを提供できる。
来店客(アクセス客)に差別なく、「ご無理ごもっとも」で待遇する「おもてなし」に、本当の意味での顧客志向は存在するのだろうか? 三越の小僧読本には、どんなに無理難題をふっかけられても相手は子供だと思って、ご無理ごもっともとはぐらかし、とにかく気分よく帰ってもらえ・・・と書いてある。「一瞬間とも油断せず、いちいちお客様の脈を取らぬまでに、親切、用意、慇懃、正直、機敏、あらゆるさじ加減をもちいるべきであり」とも書いてある。
こういったやり方を非難しているわけではない。私もサイト上や店舗内で、こういうふうに待遇してもらえば、さぞかし気分がよくなるだろうと思う(もっとも、客を子供だとみなすから、客も自分は子供みたいにダダをこねてもよいという気持ちになる。だから、店員に暴力をふるったり土下座させたりといった、大人らしからぬふるまいに及ぶのだと考えることもできる)。
「おもてなし」の顧客志向はホンモノなのだろうか?
ちょっと古い本だが、1980年代初めに出版され世界的ベストセラーになった「エクセレント・カンパニー」のなかに、「超優良企業の価値観は、いつもかならず強い顧客志向に基づいている。言い換えれば外部志向が人一倍強い。したがって、超優良企業は、環境の変化には並はずれて敏感であり、競争会社よりも適応力に勝るということがいえる」という箇所がある。
「おもてなし」の心理は受動的である。来店してきた客、アクセスしてきた客に、その時の気分を含めてパーソナライズされたサービスを提供し、満足してお帰りいただく。これを外部志向が強いといえるだろうか? 自分たちが創り管理する世界にやってきた客を満足させ外に送り出す。自分たち独自の世界観をつくるプロセスは、どちらかといえば内向き志向であり、外の環境の変化に並はずれて敏感だとはいえないのではないか?
エクセレント・カンパニーに取り上げられた企業のいくつかが、その後の、不安定な経済状況を乗り切ることができなかったのは、彼らの顧客志向がホンモノでなかったからかもしれない。
おもてなしのメンタリティはあくまで受け身。外に出て客を引っ張ってこようという能動性はない。
日本企業はマーケティングが下手だという評判は、海外ではすっかり定着しているらしい。最近でもAdvertisingAgeに「日本企業はマーケティングがなんであるか理解していない」と書かれていた。それは、日本企業に外に出て客を引っ張ってくる能動性、店舗やネットにアクセスする気がない客の考えを変えてアクセスするように仕向ける積極性がないことを指摘していることに他ならない。やってきた客には考えられうる限りの気配りサービスを提供するのに、やってくるように仕向けるプロセスには無関心なのだ。そういったプロセスにはそれなりのテクニックもいるのに、それを修得し使用する気がないということなのだ。
だから、不景気になって消費者がひきこもるようになり、自分たちの世界(領域)にやってこなくなると、手のうちようがなくなり、一番知恵のない方法、つまり安売りに走る。
マーケティング上手といわれる韓国の自動車メーカー「ヒュンダイ」は、2008年の金融危機後、米国における自動車の売上が下がるなか、巧妙なキャンペーンを始めた。ローンを組んでクルマを買ったとして、失業したら、どうやって残りのローンを払うのか?・・・不安から買い控える消費者たちに「ヒュンダイの安心保証」を提供した。ヒュンダイのクルマを買った後1年以内に失業した人たちに、自動車を買戻すことを保証したのだ。結果、2009年の売上は、他メーカーが軒並み落ちたににもかかわらず8%伸びた。実際に買戻す結果となった客数は350人だった。GMのようなメーカーも、その後、同じようなキャンペーンを実施したが、ヒュンダイほどには成功しなかった。
東日本大震災が発生したわずか1か月後。不要不急な商品を買い控える消費者が多いなか、デビアスのフォーエバーマークは8万円もするダイヤ入りコードブレスレットを販売するのに成功した。コードブレスレットには愛情や安心感をいだかせるストーリーがあった。また、代金8万円の一部を被災地の子供を援助するNPO法人に寄付する仕組みもあり、贅沢品のジュエリーを買うことへの罪悪感も消し去ることができた。わずか6か月で1800万円近くの寄付金が集まったというから、価格の5%を寄附したとして、20倍の3億6000万円(4500本のブレスレット)を販売したことになる。
2つのケースは、顧客の心理を深く洞察し、積極的にメッセージを送ることで、買うのをやめようとする気持ちを変えるのに成功した例だ。そのうえ、消費者をハッピーにした・・・とまでいかなくても、当時一番必要だった安心感を提供することに成功した。これは「おもてなし」ではない。だが、売り手が顧客に注意や意識、考えを専念させた結果だろう。ホンモノの顧客志向である。
おもてなしを批判するつもりはさらさらない。だが、あくまで受動的な「おもてなし」を顧客志向だと考える風潮はいただけない。企業はもっと積極的に外に出て、自分の領域に客をひっぱってくるくらいの気持ちでなくては、マーケティングに上達することはない。
東京オリンピック招致のために、日本チームが日本人らしからぬ積極的態度でのぞんだように・・・。
Copyrights 2013 by Kazuko Rudy, All rights reserved.