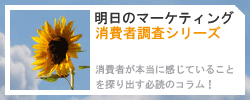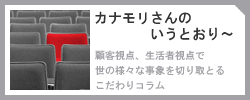資生堂の新しい人事が話題になっている。
3月31日に、2年前に52歳で社長に抜擢された末川社長が退任し、前社長だった前田会長が社長も兼任することになった。資生堂は2008年秋のリーマンショック以降、連結売上高は6400億円から6900億円レベルで停滞気味。営業利益もマイナスが続いていた。しかも、12年度3月期まで6期連続、四半期ごとに業績の下方修正を繰り返すことで、市場の信頼も損なわれていた。
業績不振の理由がいくつか挙げられているが、驚くべきことに(というか、過去に何度も繰り返されてきた理由なので、あまり驚かない。驚かないということ自体が、一番驚くべきことなのです。ああ~ややこし!)・・・。とにかく、国内市場の不振の主な要因は、実は、もう1980年代には明らかにされていたことなのです。それが、30年たっても解決できなかったという一言につきる。
短くまとめてしまえば、今の資生堂をつくってくれたもの、つまり、日本最大の化粧品メーカーで世界でも5~6位につけるまでの成長をもたらしてくれた流通チャネル・システムが、高度成長時代がおわってからずっと、資生堂のあしかせになっているのです。
世界に通用する強力な商品ブランドを創造することもできず、そして、継続的に在庫の問題や高コストの問題に悩まされてきているのは、資生堂が自ら構築したチェインストア・ネットワーク(契約小売店網)と、これもまた自らが構築したチェインストアとの複雑な関係性のなかに、からめとられてしまった結果なのです。
もっと短くいえば、過去の成功体験が生み育てた「しがらみ」から、資生堂は抜け出すことができないでいるのです。
さきに断っておきたいのですが、私は、資生堂の戦略がまちがっていると批判するために、このブログを書いているのではないのです。過去何代もの資生堂のトップ経営陣は上に列挙したような問題についてよ~くわかっていた。一流企業のトップにまで登りつめることができた人たちなのです。頭脳的にも人間的にも優れた人たちに決まっています。が、それでも切れないのが「しがらみ」なのです。
・・・・いずれにしても、まず、資生堂のその「しがらみ」について説明させていただきます。
チェインストアと呼ばれる契約小売店は、1923年(大正12年)に、創業者の息子で初代社長の福原信三が、乱売への対策として、「資生堂製品はチェインストアだけで扱い、全国同一価格とする」と販売政策の基本を定めたことから始まります。当時、第一次大戦後の世界的不況のなか、化粧品業界では値引き競争が激化し、小売店の倒産が相次いでいました。こういった不毛の競争から取引先や商品価値を守るとともに全国市場への発展を進めるために、アメリカで発達していたチェインストア・システムを採用したのです。そして、このチェインストア組織をより強固なものにするために、全国の主な問屋と「資生堂契約店舗には同じ価格で卸売りする」という契約を結ぶ。問屋は、その後、資生堂の特定代理店となり、最終的には、こういった特定代理店と合併したり共同出資したりして「資生堂製品のみを専門的に流通させるための組織」として「系列販売会社」を各地に設立することになりました。
第二次大戦前にできあがった資生堂の流通システムは、戦後、壊滅打撃からすばやく立ちあがり、全国津々浦々にまで広がったチェインストア・ネットワークはその後の資生堂の高度成長を支えてくれたのです。
化粧品業界は60年代~70年代にかけて不況知らずの産業といわれました。戦後生まれのもっとも人口の多い「団塊の世代」の女性が結婚前の独身女性であったころで、化粧品はよく売れました。新製品を出してマス広告で宣伝すれば売れた。が、この「団塊の世代」女性が結婚して子供が生まれるようになったころから、化粧品需要も落ちてくる。80年代になると、少子化問題に加えて海外ブランドの参入によって競争は激化する。
こうなると、どうなるか?
まず第一に、売上ノルマを達成するために、営業担当者は各小売店に在庫がまだあるのを知ったうえで、仕入れてくれるよう頭を下げる。「お願い販売」というか「押し売り販売」だ。店頭の売上があがっていなくても、仕入れの時点で売上として計上してしまう。そして、第二に、小売店は目新しい新製品があれば売りやすいので、新ブランドや新製品を出すように要望する。押し売り販売で借りがある営業としてはじゃけんに断れないし、新製品なら店も仕入れてくれるので、資生堂本社に新製品の発売を強く要望する。新ブランドや新製品を出せば売上は広告宣伝活動によって一時的に上がる。が、長続きはしないので在庫となる。
(小売店には仕入れ額に応じてリベートが支払われた。だから、小売店も売れる見込がなくても仕入れてしまう。2001年には、リベートも仕入れ時ではなく、店頭販売実績で支払われることに契約を変更。同時に、営業担当者の評価も販売実績に切りかえられました。しかし、長年つづいた仕入れ額を実績とする仕組みは、最初に書いたように『資生堂が自ら構築して自らがからめとられてしまった、系列販売会社や契約小売店との複雑な関係性』をつくった要因のひとつなのです)
当時は、他の産業でもよくみられる光景でした。日本では、家電メーカーも、たとえば、松下電器(いまのパナソニック)なども同じようにチェインストアをかかえていたから、小売店の要望に応える形で、一年ごとにモデルチェンジをしていました。資生堂のような化粧品メーカーにとっても、松下電器のような家電メーカーにとっても、お客様は系列販売会社の社長だったり契約小売店の主人であり、消費者ではなかったのです。B2C(対消費者販売)をしていたのではなく、B2B(対企業販売)をしていたようなものです。だから、信頼できる一流会社のイメージを築くための企業ブランディングが中心となり、(新製品や新ブランドをつぎからつぎへと出していたというブランド軽視からも明らかなように)商品ブランディングはおろそかになってしまったのです。
ブランド戦略論で有名で、日本でも幾冊かの本を出しているデイビッド・アーカーは、2001年に電通の招きで日本をおとずれたときに、「日本ではブランド=企業ブランドととらえる向きが多すぎる」と語っています。
資生堂の決算内容をみると、大幅な減益を覚悟して大量の流通在庫を削減する試みは、過去何度もおこなわれています。
最初は1987年。創業者の孫ということで、社内外からの抵抗をかわすことが期待されたのでしょう。福原義春社長の就任がきまるとすぐに、販売会社や小売店にたまった大量在庫の処分がきめられた。販売会社への出荷額を絞るとともに、2年間にわたって約200億円の在庫償却を実施。12期連続増収増益から一転して経常利益が49%減となりました。
しかし、在庫は1998年3月期には国内で500億円。海外をあわせると713億円に達するまで、また増えてしまった。売上ノルマ達成のための押し込み販売があいかわらず続いていたのだ。
2001年度には、430億円の流通在庫を処分したために、220億円の赤字を計上する結果となっている。当時の池田社長は、「再点検したところ、小売店、販社、工場、いたるところに偏在在庫が蓄積されていた。売上げを上げるためにお願い販売をして、あとで返品として受け取ることが日常化していた」とコメントし、対策として、「小売店にPOS導入をお願いして、卸の数字で売上をたてるのではなく、店頭売上を資生堂の売上と結びつけるようにする」と語った。また、「在庫をつくった原因は100にも及ぶブランド数にあるので、今後は35ブランドくらいに減らす」とも語った。「(将来のために)ウミを出し切る」と池田社長は記者会見で宣言している。
結局、1987年からの14年間、一時的に売上を上げるための押し売り販売や新製品発売の悪しき習慣もなくなることはなかったのか? あるいは、バブル崩壊後の90年代の売上不振、またファンケルやDHCなどの通販化粧品の新規参入による競争激化のなか、悪しき習慣が復活したのか? いずれにしても、90年代の10年間で64ものブランドが新発売されている。
2005年、前田社長が就任して「旧来のしがらみを断ちきる」と宣言。ブランド数をへらしてメガブランドに投資を集中するという、当時すでにユニリーバとかP&Gが推し進めていたパワーブランド戦略を採用することを明らかにした。そして、2006年には「ツバキ」に50億円という過去最高の宣伝広告費投入し、これがメガブランド育成作戦だと世の中にしらしめた。2007年には、8つの重点ブランドで売り上げの49%、27の主軸ブランドで総売り上げの80%以上・・・とブランド戦略が順調にいっていることを説明していたのだが・・・・。
どうも、この「改革」は、景気悪化もあったし、それから社内外の抵抗もあったらしく、途中で、最初の勢いはなくなってしまったようだ。
2011年、52歳という若さを期待された末川社長が発表した新しい3か年計画では、過去の成功体験からの決別が、またまた、宣言された。「デ・ジャヴ」感があるけれど、会見では次のようなことが語られた。
1.新製品に依存しすぎで、1年で寿命が終わる製品が多すぎる。ロングセラー商品が育っていない。当然のことながらブランドアイデンティティも希薄。
2.流通在庫の問題もいまだにある(このとき、どれだけの在庫があるかは明らかにされなかったが、販促物の不良在庫関連コストだけでも年間数十億円になっていることは明らかにされた)。
3.ネット販売に挑戦する。(このとき、社長は「専門店は資生堂が苦しかった時に助けてくれた店ではあるが」、でも、ネット販売にあえてチャレンジすると語った。この言葉からも、契約小売店が店舗売上が落ちることを懸念して、ネット販売に長い間強く反対していたことがよく理解できる)。
その末川社長が自分の健康上の理由から2年後に辞任。「尽きない悩みと各所からのプレッシャーに、末川氏は周囲に『なかなか眠れない』と漏らしていたという」と週刊東洋経済記事には書かれていた。日経MJ記事にも、「資生堂には歴代トップからなる「相談役会」もあって、『歴代トップの間で(末川社長への)批判が強かった』と資生堂関係者は語る」と書かれていた。どうやら末川社長は社内外の風当たりの強さに疲労困憊してしまったようだ。
「しがらみ」ストーリーのまとめに入ります。
まず、企業ブランドと商品ブランドの話です。
資生堂は企業ブランドを築くことには成功した。信頼できる企業、一流企業・・・こういったイメージは小売店網を拡大するのには強い武器となった。だが、「消費者をお客様とする」マーケティング戦略をとることをしなかった(あるいは、できなかった)資生堂は、商品ブランドを築くことはできなかった。その証拠というか、日経BPによるブランド・ジャパンの過去10年間の調査において、資生堂はビジネスパーソンによる評価では常に50位以内にはいっている。が、消費者による評価では、2006年に前年度の108位から42位にはいったのが最高位(たぶん、ツバキの大々的キャンペーンのせいだろう)。他の年には50位以内に入っていない。
これはやっぱりおかしい。
消費財を販売しているメーカーなら、その逆の現象でしかるべきだろう。資生堂という名前がランキングに入っていなくても、ツバキとかマキアージュが上位にランクされている・・・というならよい。が、それもない。
化粧品業界で、企業ブランドで成功した企業は見当たらない。もちろん、企業ブランド=商品ブランドになっているシャネルとかは別である。化粧品メーカー世界ランキングで一位や二位をしめるP&Gやロレアルは企業ブランドとしても有名ではあるが、ロレアル傘下のランコム、へレナルビンスタイン、シュウウエムラ、メイベリンニューヨークはそれぞれ独立したブランドとして著名だ。一般消費者の多くは、シュウウエムラの親会社がロレアルだなんて知らないだろう。ブランドは個性なんだから、知らないほうがいい。資生堂と世界売上で5位6位を争っているエスティローダでも、クリニック、ボビーブラウン、マック、ドゥ・ラメール、オリジン、アラミス等々。いずれも、日本のデパートの化粧品売り場に別々のカウンターをかまえているが、それぞれが同じ企業グループに属しているなんて、買い物客の大半は知らないだろう。それが商品ブランドだと思う。
資生堂の契約小売店の売上は、90年代初めには、国内総売り上げの75%を占めていた。が、いまでは、売上シェアは25%程度に落ちてきている。が、しかし、新しい販売チャネル、たとえばドラッグストア、コンビニ、そしてネット販売への対策は、契約店への遠慮があって思い切った挑戦ができていない。ネット販売にしても、2012年になってやっと参入することになったが、これも、契約店に納得してもらうために中途半端なもので終わっている。
もちろん、資生堂だって、こういった問題点はずっと前からわかっている。歴代の経営陣だって、何をすべきかはわかっていたはずだ。だが、わかっていても実行をするためには、社内外の「しがらみ」を切り捨てなくてはいけない。考えてもみてほしい。若いころからずっと、自分の成績、あるいは会社の成績をあげるために、頭をさげて販社や小売店に無理して頼み込んでいるのだ。えらくなって社長になったからといって、昔受けた恩義を裏切ることなど、フツーの人間の神経ではできやしない。あるいは、また、自分がこれまでお世話になってきた先輩を、とくに自分に目をかけて昇進を導いてくれた先輩の意見を、社長になったからといって否定することはできるだろうか?
むつかしい。むつかしいからこそ、一番最初に流通在庫に大ナタをふるったのは創業者の孫であり、また、2011年には、若くてしがらみの少ない社長が選ばれているのだ。
それでも、過去のしがらみをたちきることはなかなかできない。過去のしがらみを切ることは自分史そのものを否定するようなものだ。よほど無神経な人間でなければできないだろう。だが、無神経な人間では、会社の上には立てない。
それがわかっているから、海外の会社であれば社外取締役が選んだ外部からの人間をもってくる。
有名な成功例がIBMです。IBMは1992年度に81億ドルにも及ぶ損失を出しました。この数字は、当時のアメリカのビジネス史において一つの企業が出した過去最大の赤字額です。IBMは1911年創業以来、常に生え抜きの社員が社長に就任してきました。が、破産寸前になって、大きな外科手術が必要になったとき、外部から、しかもコンピュータとは全く無縁な食料品メーカーRJRナビスコのCEOであったルイス・ガースナーを雇いました。
ガースナーは8万人余の人員を削減するとともに、コンピュータという機械を販売していた会社を、クライエントが望むような機能をはたすコンピュータ・システムを提案し提供できるサービス会社に変身させることで、IBMを再生させることに成功しました。
外部の人間を雇った成功例です。
もちろん失敗例もある。ソニーのストリンガー前CEOは、米国ソニーの社長をしていたのだから外部の人間ではないけれど、外国人ということで、しがらみなく改革がしやすいはずだった。実際、世界中で3万人に及ぶ人員削減や工場閉鎖をしたが、本当は、それでも足りなかったらしく、外国メディアでは「社内の抵抗勢力のせいでリストラが思ったようにできなかった」と発言している。もっとも、リストラをしながらも自分は8億円の高額報酬を得ていたことを批判され、また、リストラをする一方でその後の方向性を明確にしなかったと国内では非難された。
日本の終身雇用制度は日本固有の文化と結びつけられて考えられる傾向があるけれども、この制度は戦後の高度成長期における労働力不足のなか、従業員のためというよりは会社のために出来上がった制度で、戦前にはとくに意識された社会的制度とはなっていなかった。アメリカでもP&Gとかウォルマートとか、地方の中小都市に本社を置く企業では、地方都市における家族を大事にする暮らしぶりやライフスタイルのため、自然と一生同じ会社で働く社員が多かった。そういった会社でも、最近の不安的な経済環境のなか、生え抜きでない社員が社長やCEOになる傾向がある。そのほうが、しがらみがないぶん、改革を果断に進めることができる。社長やCEOの場合は、中途採用とはいわないかもしれないけれど、いずれにしても、「いま、ここにある危機」を乗り切るためには、外部からの人間のほうが適切なのでしょう。
だいたいにおいて、長寿ブランドを築くためには外部の人間が必要なときがある。なぜなら、同じブランドにずっと接していると、自分で自分の大切なブランドの価値がわからなくなってくるから。会社に入社してからずっと同じブランドに接していると、飽きてくる。売上数字がさがってくると、「ああ、このブランドももう寿命かな」と考えてしまう。効果的な販促活動は、すべてしてしまったような気がする。時代は変化して消費者も変化しているのだから、過去にやった販促活動をまたしてもよいかもしれない。が、自分が5年前や10年前にしたことと同じようなことをするなんて・・・。「ああ、あれはダメ。以前、もうやって、あんまり結果もよくなかったから」と、つい口にしてしまう。
外部の人間で、消費者としてそのブランドを好きで愛している人を中途採用で雇うことは、長寿ブランドを築くためには必要だと思います。
そのブランドについて熟知していると思い込んでいる社内生え抜きの人間だけがマーケティングを担当するよりは、、そのブランドが好きな中途採用された人間もチームに加わったほうがよい・・・と思っています。
参考文献: 1.「資生堂、3つの失速」、日経MJ 3/13/13、2.資生堂「改革」振り出しに、日経新聞、3/12/13、3.資生堂「末川価格」定番磨く、日経MJ 9/2/11、4.「新製品には頼らない」 日経ビジネス 7/4/11、5.「再登板で清算なるか、資生堂の負の遺産」、週刊東洋経済 3/23/13、 6.「禁断のネット販売開始、悩める資生堂の賭け」、週刊東洋経済 4/21/12、7.「ブランド削減に着手」 日経産業新聞 1/4/08、 8.「資生堂 漂流」 日経産業新聞 11/07/01、 9.「分社化や系列店 色分け、年代別のブランド再生」 日経ビジネス 6/22/92、10.「がけっぷちの定価販売 莫大な販管費圧縮急ぐ」 日経ビジネス 11/08/93、 11『店頭からの全社改革」 日経流通新聞 7/23/02、 12.「ブランド集約しチェーン店再生に注力」 日経ビジネス 4/09/01、13.「ブランド再編 世界に挑む」 日経ビジネス 5/15/2000、14.「企業ブランドの集合体に」 日経産業新聞 7/06/2000、15.「資生堂 ブランド再編へ新旧交代」 日経産業新聞 10/27/99、 16.「利益重視、聖域にメス」 日経産業新聞 8/31/99、 17.「現場主義やゆずらず」 日本経済新聞 10/05/98、18.「日本企業、ブランド価値高めるためには・・・」、日経産業新聞 11/21/01、19.山本敦「戦前の資生堂にみる日本的マーケティングチャネルの形成」
Copyright 2013 by Kazuko Rudy. All rights reserved.