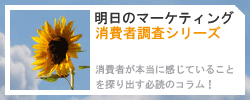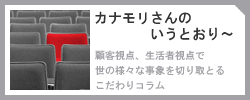今日特売でキャベツが80円ですって!
ソーシャルメディア(Social Media)の定義についてはまだ明確に定まったものがないようだ。でも、ソーシャルメディアを使った例を挙げろといわれれば、ブログ、Wikipedia 、SNSのFacebook、 MySpace、 Mixi 、動画共有の YouTube、そして、マイクロブロッギングとSNSのTwitter、仮想世界のSecond Life・・・・・などの名前が浮かんでくるはずだ。
マーケッターなら一番関心があるのはSNSを使ってのクチコミだろう。TVというマスメディアの威力が落ちているなか、コスト安に数百万人、数千万人にメッセージを到達できる可能性は魅力的だ。ただし、到達数はわかっても、その効果の程度がわからない。効果的な測定方法もわかっていないのが現状だ。クチコミ・マーケティングに注目が集中しているせいか、欧米大手企業のマーケティング担当役員からなるMENG協会の調査(2008年10月)によると、会員の75%が「ソーシャルメディアはユーザー間の会話に基づくメディアである」という定義で満足しているそうだ。
日本では、携帯電話で「リアルタイム日記」と呼ばれる簡易ブログを使って、1・2行くらいの短い「ひとりごと」や「つぶやき」を書き込む女子高校生のことが話題になった。アメリカでも、FacebookやTwitterを使った若者同士のコミュニケーション、とくに、自分の一挙一動をリアルタイムに絶え間なく書き込む行為については、「そういうことをする意味がとんとわからん」と「大人」たちが悩ましげに首を振っている。
だが、こういったデジタル・コミュニケーションに関する記事のなかには、大人たちからみた「無意味さ」に重要な意味を見出そうとする内容のものもある。
まず、「進化心理学者はソーシャルネットワーキングについて何を語っているか?」と題された記事を紹介しよう(参考文献1)。進化心理学は、限りなくサルに近かった我々の祖先たちが、アフリカの大草原で生存するために獲得したメンタリティを研究することで、現代の我々がなぜそう感じなぜそう行動するのかを理解しようとする学問だ。たとえば、英国の人類学者であり進化心理学者としても有名なロビン・ダンバーの本(日本語訳は「ことばの起源-猿の毛づくろい、人のゴシップ」青土社)には、ゴシップ(うわさ話)の起源は毛づくろいにあるという説が展開される。
旧石器時代に登場したサルに近い我々の祖先にとって、グループのなかにおける自分の「位置」を知っていることは生き残るための必須条件だった。グループのメンバー同士の関係、たとえば、誰と誰がセックスし、誰と誰が仲良しで、誰と誰がケンカしたといった情報を知っていることは、組織のなかで生存し、自分の地位を維持し、あるいは権力の階段を上がっていくためには欠かせない知識だった。それがゴシップ(ウワサ話)の始まりだ。だが、当時、彼らは、まだ言葉を持っていなかった。言語が生まれる前にゴシップはどう伝達されたのか? 互いに毛づくろいすることによって情報が伝達された・・・とダンバーはいう。いまでもチンパンジーは互いにシラミをとりあうのに一日の20%を費やすという。毛づくろいは太古の昔のソーシャルネットワーキングなのだ。
だが、ある時点になると、グループのメンバーの数が余りに大きくなりすぎて、いかに元気で出世意欲マンマンの若手でも、メンバー全員の毛づくろいをすることが不可能になった。それが言語の始まりだ。言語が生まれたのは50万年から 100万年くらい前。きちんとした話し言葉が使われるようになったのは25万年前だといわれる。言語によって情報交換できるようになったおかげで、情報は早く伝達されるようになったし、また、同時に多人数に伝えることもできるようになった。
つまり、人間のゴシップ好きは祖先の祖先である猿人から遺伝的に受けついだものなのだ。
この観点からMixiとかFacebookとかいったソーシャルネットワーキング・サービスにおける友人の数を調べてみると面白い。
ダンバーによると、言語が生まれる前の人間たちにとって適切なグループの規模は50人(ヒヒやチンパンジーの群れのサイズと同じ)くらいだったが、言葉が生まれることによってこれが150人ほどまで増大したという。150人は新石器時代の村の規模だが、この数は、いまでも、ひとつの組織(たとえば、軍隊や企業内の機能単位)に適切なサイズだと考えられている。つまり、グループ内のメンバーがほどよく適当に接触できる最適規模は、過去1万年の間、まったく変化していないのだ。
しかし・・・・だ。ネット上で最も社交的な人間は、数百人、いや1000人を「友人」として持っている者もいる。もっとも、よくよく調べてみると、「友人」の中身は2つに分かれていて、親密な「友人」グループの数は余り変化しない。が、それ以外の「弱いつながり」のゆるやかな関係にある知人の数は制限なく増える。それが、「友人」1000人の実態なのだ。ネットワーク理論によれば、この「弱いつながり」というのが、ある意味、非常に役立つネットワークとなる。なぜなら、親密な「友人」は社会的階層、職業、趣味などで共通している点が多く、結果、自分の友人の友人のそのまた友人が自分の友人だった・・・ということが多い。だから、たとえば、仕事を探しているとして、親密な「友人」ネットワークに「誰かコネを紹介してくれ!」とメッセージを送っても、紹介された人物を自分はすでに知っていたとか、同じ人物を紹介されるとかいうことになる。反対に、「弱いつながりの友人たち」にメッセージを送ったほうが有力な情報が得られる確率が高い。クチコミによる流行においても、「弱いつながり」が存在しないと流行には至らないことが理論化されている。
・・・ということは、我々人類は、テクノロジーの助けを借りて、グループの効率的規模を増大することに成功したといえるのか? いやいや、「弱いつながり」であるゆるやかな関係においては、メッセージの伝達スピードや広がりは偶然に左右されることが多く、それを自分が効率的に管理運営できるグループだとみなすことはできないだろう。しかし、「弱いつながり」ネットワークにおけるメッセージの伝達とその結果(効果)を数値化できるようになれば(つまりクチコミの管理ができるようになるということだが)、それは、マーケティング上の革新的進歩であるとともに、人間が過去1万年の間に超えることができなかった限界を超えたということになるのではないだろうか・・・・?
ちなみに、「Journal of Computer-Mediated Communication」に2008年に発表された調査結果によると、アメリカの大学生はFacebookで友人の数が302人と申告している人間が交際するには最もクールな相手だと見ているようだ(Facebookで、友人の数以外はまったく同じプロフィールの人間が紹介され、誰が社会的に最も魅力的に思えるかのランクづけをしてもらったのだ。友人の数は102、302、502、702、902人となっていた。302人より上になるとSNS依存症と思われ、302人以下は社会的対応能力のないやつとみなされた)。少なくとも、大学生たちは、自分たちが無理なく取り扱うことができるグループの数は 150人を超えていると考えているようだ。
(2006年に実施された日本のMixiに関する調査(参考文献5)では友人数は平均81人となっていたが、Mixiモービル利用の若い世代だけを対象にした調査ならもっと多くなっていたかもしれない。SNSの友人数というわけではないが、2004年に博報堂が実施した「首都圏に住む10代後半の男子」を対象とした調査では、ケータイの登録人数の平均は71.66人で、 350人という例もあったという)。
紹介したいもう一つの記事は2008年9月にウォールストリートジャーナルに掲載されたものだ(参考文献2)。ここでは、FacebookやTwitterにおける友人関係を「大人」たちが実際に数ヶ月間経験してみて、若者たちがなぜ魅了されるのか、なんとなく理解できたという経験が記されている。
「まるで、小さな村の人間関係が再現したようだ」・・・・と、SNSを利用し始めたジャーナリストはコメントしている。Twitterで自分がいま何をしているか短いメッセージを継続的に書き込む。もちろん、それをきちんと時系列で読む友人はいないかもしれない。だが、「風邪をひいたみたいだ」という10日ほど前に書いたコメントをなにげなく見ていた友人がいて、その後のコメントをなんとなく気にしていて、最近書き込みが少なくなったような気がしたからと、「どう?風邪のぐあいは?」とメールしてくる。あるいは、場合によっては、家まで見舞いにきてくれるかもしれない。実際、その友人とは一年ほど会ってはいなかったのに、互いにネットを通じて、なんとなく相手の動性がわかっていたので、一年間の無沙汰などなかったように、すぐに話が通じる。こういった絶え間のないコンタクトが生む意識は、「ambient awareness」だと説明される。
ambient awareness・・・なんとなくまわりの空気とか雰囲気といったものに気がつく、あるいは意識する・・・といったような意味。
たとえば、アガサ・クリスティの探偵小説シリーズ「ミス・マープル」を思い出してしください。ミス・マープルが住んでいる小さな村では、誰もが他の誰が何をしているのかなんとなく知っている。退役軍人Aはいつも9時には家を出て一時間散歩する。未亡人Bは毎週水曜日にはパン屋でパンを買う。だから、未亡人Bが水曜日にパン屋に通じる道を歩いていなかったら何かおかしいと気づく人たちが幾人かいる。あるいは、また、その村に生まれ育った男がいたとすれば、その子が三歳のときに隣の女の子にケガをさせたとか、6歳のときに川におぼれそうになったとか、彼の半生についての情報を知っている人間がたくさんいる。
同じようなことがSNSで起こっている。ネットが存在しなかったころと比較すると、いまでは、一度知り合ったら縁が切れるということがない。小学一年の同窓生とフェースブックで再会して、その後、相手の書き込みを時々なんとなく読んだりしているから、互いになんとなく相手の生活がわかっている。出張先で知り合ったビジネスマンも、いったん「友人」の中に入れば、一生ある程度の弱い関係は維持される。
100人~300人くらいの「友人」たちと、絶え間なく、Ambient Awarenessの関係を保つ。Ambient Awarenessには、日本語でいうところのKY「空気を読む」と共通点があるかもしれない。互いに相手の空気を読むことができる関係を多くの友人たちと築くことができる。「友人」同士は、空気を読んでタイミングよく適切な内容で連絡する。こういった関係では、昔の「わずらわしいこともあるけれど淋しくはない村の暮らし」が再現される。SNSの人気は社会的孤立への反動だとウォールストリートジャーナルの記事は主張する。
「いまの世代は友人との関係が切れるということがありません。これは歴史的にみてごく普通のことなのです・・・人類の歴史をたどれば、転々とした人生を送り、新しい関係から新しい関係へと放浪を続けるということは、非常に新しい 20世紀特有の現象なのです。・・・心理学者や社会学者は人間が都会における匿名の存在に適応することができるかどうかを問題にしてきました・・・・」 。が、ネットの登場によって、歴史が逆戻りしはじめている。
日本でも、「ネットを通じてしか関係性を持てない若者たち」的見方しかしない「大人」が多い。が、こういった観点から見直してみると、なんだかまったく明るい・・・というか牧歌的人間関係の未来がみえてくる。
もっとも、それを、進化とみるかどうかはむつかしいところだ。産業革命後の一世紀のうちに増大した社会的孤立や都会におけるわびしい個人の存在から、テクノロジーを使いこなすことで脱却し、昔の村の生活をとりもどす若者たち・・・果たしてこれを「進化した」と形容することができるだろうか? それとも、結局、我々21世紀の人間は、石器時代の祖先のおサルさんたちと比べて精神的にはなんら進化していない・・・とみるべきなのか?
いずれにしても、ソーシャルメディアの登場は、マーケティングにおいても、テレビが発明されたのと同じくらい非常に重要な出来事であることは明らかだ。最初にあげたMENG協会の調査でも、会員の67%がソーシャルメディアをマーケティング目的に利用することにおいては初心者だと答えながらも、同じく67%が2009年には予算を増大すると答えている。多くの企業は、クチコミの試みはいまだヒットする場合と失敗する場合があり、その試みのなかに規則性を見出すまでに至っていない・・・と答えている。
ミス・マープルは、小さな村のゴシップとAmbient Awarenessを利用して殺人事件を解決した。同じように、PCかケータイを手に、いくつかのSNSに会員登録をしている人物が、「友人」302人からの情報をもとに、世にも不思議な殺人事件を、部屋から一歩も出ることなく解決する・・・・・そんな探偵小説がいつかきっとベストセラーになるだろうと私は推理します。えっ? もう、とっくの昔に出版されてるって!?
参考文献:1. Michael Rogers, What evolutionary psychology says about social networking, MSNBC.com, 9/10/07, 2.Clive Thompson, Brave New World of Digital Intimacy, The New York Times, 98/7/08 3. Matthew Hutson, What’s the Optimal Number of Facebook Friends?, Brainstorm, 1/28/09 4. Social Media Practices Still in Infancy Stages Says Marketing Executives Networking Group, 11/6/08、5.山内みどり、SNSにおける自己開示度・類似度が対人的魅力に及ぼす効果
Copyright 2009 by Kazuko Rudy. All rights reserved.