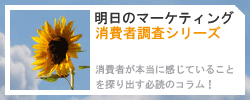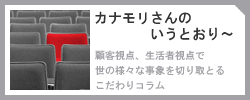不確実とは英語でUncertainty。不確実性の定義として有名なのは、ケインズと同時代のアメリカの経済学者フランクリン・ナイトが1921年の論文で提案したもの。彼は、不確実性にも2種類あり、確率で推し量れるものをリスク(Risk)とし、確率では表現できないものを本当の不確実性とした。
この定義でいけば、天候も容認できる確率で予測できる限りはリスクとなり、最近のように冷夏や暖冬のような長期予測もはずれるようになると不確実性の範疇に入ることになる。
ナイトのこの区別には異議を唱える経済学者も多く、どんな不確実性だって充分な情報さえあれば確率で表現することができる・・・という主張もあれば、確率というものは、そもそも、自分が信じていることを主観的に表現しただけのもので、実社会のランダムネスとは必ずしもつながっているわけではない・・・という意見もある。
いずれにしても、将来、特定の出来事が実現するかどうかわからないという不確実性に私たちは直面している(というか、直面していると私たちは信じている)。
地球温暖化によるといわれる異常気象。気象に関する不確実性は、科学が発達することにより、高い確率でゲリラ豪雨、旱魃、突風なども予測できるようになれば、対策がとれるリスクの問題に変わっていくかもしれない。だが、株価の乱高下とか、そういった不安定な株式市場が消費者心理ひいては消費者行動にもたらす影響を予測することは、不特定多数の人間の意思決定の問題となり、数字で予測することが不可能な本当の意味での不確実性となる。
将来何が起こるかの可能性を客観的に数字で予測できにくい不確実な状況下においては、「人々は一般に理性より情動や直感に基づく行動をとりがちになる。また、確たる根拠のないままの判断ゆえ、他のひとに影響されやすく、状況次第で大きく行動を変えがちになる(1)」といわれる。「ブランドと感情と記憶」シリーズで書いたように、人間の意思決定は、根本的には内なる感情(情動)によって左右される。とくに充分な情報が存在しない状況においては、消費者はヒューリスティクスや直感によって判断する傾向が高くなる。
あるいは、また、「不可解な消費者行動」シリーズで書いたように、人間には行動経済学でいうところの「損失回避性」がある。不安定な社会状況においては、とくに、現状維持バイアスが強くなり、お金は使わない、子供は生まない、新しいことにはチャレンジしない・・・・ということで、余計に景気が悪くなるという説明のしかたもできる。行動経済学の始まりを告げた1979年の論文「プロスペクト理論:リスク下での決定」の著者の一人であるダニエル・カーネマンは、2002年にノーベル経済学賞を受賞している。選考理由は、「経済学に心理学研究からの新しい識見を採用し、とくに、不確実性下における人間の判断と意思決定において顕著な業績を残した・・・」となっている。行動経済学は、まさに、いまの時代にふさわしい学問なのだ。
いずれにしても、不確実な市場環境における消費者行動は感情優位となり、ヒューリスティックな判断をする傾向が強くなる。(最近のTVニュースで百貨店の担当者が株の上がり下がりによって客足が違ってくるとコメントしていた。株の売買などしたことがない消費者でも、株が大幅に下がったと報道されると購買を控える。消費者は株の高低というキュー(手がかり情報)を使って景気の先行きの判断をしているわけだ。このように、1)経済の実態とは少し離れたところで判断が下されて株が乱高下し、2)株式市場とは少し離れたところで判断が下されて小売店舗での売上が上下する。まさしく、不特定多数の意志決定者の行動が他の不特定多数の意志決定者の行動に影響をあたえることにより、結果として、予測しがたい大きな変化が生み出されたことになる)。
こういった状況において小売市場で重要なことは、(実際には、いつの時代においても重要なことではあるが・・・)、内なる感情に訴えることができるブランドを確立し堅持することだ。メーカーは内なる感情を動かすことができるブランドをもっていれば、小売の値下げ圧力にも屈する必要はなくなる。そして、NBメーカーが強いブランドを持っていることは、小売店にとっても大切なことなのだ。
消費者の買い控えが始まると、「低価格」「値下げ」の2つ言葉がマジナイのように唱えられる。だが、不景気には低価格商品というのは、あまりに短絡的すぎないか?小売店が2つ言葉のマジナイを繰り返すことは、自分たちの本来の任務は消費者のための購買代理業であることを忘れていることを告白しているようなものだ。
面白いデータがある。アメリカの大恐慌時代(1929年~30年代初め)において、もっとも厳しかった1933年でさえも、化粧品の売上は恐慌が始まる以前より高くなっていた。そして、1939年の売上は10年前よりも(実質成長において)35%高くなっていたのだ。
人間は一度覚えたライフスタイルや生活水準を落とすことはなかなかできない。他のものを削っても、これだけは贅沢したいというものはある。日本だけではなく世界的にも消費者の二極化あるいは消費の二極化が存在している。なのに、スーパーは安いものばかり並べてもよいのか? 通常は特売品や安いPBを購買していても、金曜日には高級ワインと高級素材あるは高級惣菜で一週間に一度の贅沢をしよう・・・と考える消費者は多いはずだ。だが、いまのスーパーの棚に贅沢だと知覚できるような商品を見つけることはできるだろうか? 瑣末なことで差別化された似たような価格帯で似たような外見のものばかり。価格やパッケージでヒューリスティクスに選択判断しようとしても、キュー(手がかり情報)すら見つけられない。
消費者のなかには、高いほうが高品質の高級品だと判断して選択する人も多い。つまり、低価格PBがあって、初めて、それと比較して高い価格のNBの価値が知覚されるようになるのだ。ネスレ日本のジョンソン会長&社長も次ぎのように語っている。「・・・割安なPBはNBがあってこそ価値が見えるものです。当社は特定の小売向けに専用商品をつくることはありますが、PB生産はしません」。また、最近のCPG分野における値上げ傾向について、価格転嫁よりも内部努力を尽くすのが原則だとしたうえで、「一方で、無理に値上げをしないでいると業界全体のリスクになる可能性があります。日本の食品メーカーはどこも利益率が低い。製品事故や自主回収が頻発する背景には、コスト高を価格転嫁できずに収益を追う体質に一因があるように思います(2)」。
値上げするときに重要になってくるのは、消費者が知覚できる品質の違いだ。170円のNBカップヌードルと80円のPBカップヌードルがあるとして、110円の価格の差が知覚される品質の差に呼応していれば問題はない。だが、メーカーが考える品質の差と消費者が知覚する差の間に大きな隔たりがあることが多い。シリーズ第4回「NBは高くてもよいのだ」で書いたように、消費者が知覚できる品質の差を考えるときには、内なる感情とか直感が重要な役割を果たすようになる。
メーカーは製造業的メンタリティを改めなくてはいけない。以前メーカーにいたという卸業の経営者は「メーカーの商品開発の本質はラインの生産性になります。マーケティングもしていますが、多くは広告代理店などの受け売りです・・・(3)」と語っている。マーケティングが代理店まかせかどうかはさておいても、日本のメーカーが技術屋志向になりがちなことは事実だ。メーカーの経営者は、「値上げは付加価値とセットに・・・」とよく言う。付加価値という言葉を使うから、材料をXXに変えたとか、香りや風味を残すために新技術を採用した・・・とか、付け加えた価値を列挙することになる。もちろん、こういった付加した価値は重要であるにきまっている。だが、その多くが、消費者にとって、すぐに知覚できるものではない。付け加えた価値を知覚しやすいキューにして提供する、内なる感情や直感に訴求しやすい形にして提供する・・・・こういった最後のステップが抜けている例がよくある。
大手調査・コンサルティング会社のギャロップは、アメリカの小売業者や金融サービス業者(日本の小売業も含まれている)での調査結果として、企業(あるいはブランド)に満足していると答えた顧客を、その企業(ブランド)と感情的に結びついているセグメントと理性的に結びついているセグメントに分けた。そして、感情的に結びついている顧客セグメントは、財布シェア、利益性、継続性の点において、平均的顧客よりも23%も高いことを発見している(4)。
メーカーは消費者の内なる感情に結びつくブランドを確立し維持しなくてはいけない。そういったブランドはどんな時代にも、売上だけでなく利益も生み出してくれる一定の消費者セグメントを引き寄せてくれる。そして、小売店も、消費者の購買代理業として、そういったメーカーのブランド価値の維持に協力しなくてはいけないはずだ。もし、そういったブランドをメーカーが提供できないのなら、英国テスコのように高級PBとして自らが開発すべきだ。そいういった高級ブランドが存在するからこそ、低価格PBの位置づけがより明確になる(そういった意味で、低価格PBの製造元としてNBメーカーの名前をラベルに印刷することは、メーカーにとっても小売店にとってもやってはいけない愚行だとしか思えない)。
著名経営コンサルティング会社のMarakon Associatesは、小売とメーカーとの関係についていくつかの調査報告書を発表している。1993年から2002年の間における25の大手小売業者と25のCPGメーカーの業績を比較し、1) 10年の間に小売パワーがメーカーを圧倒するようになってきた、しかし、2)そのパワーは利益に反映されていないことを指摘している(これは、日本においても、イオンやセブン&アイの売上が味の素、花王、キリンホールディングスの3倍以上あっても、利益率は非常に低いのと同じだ)。理由は、当然のことながら、1)小売業の低い粗利益率、2)他社との競争は価格においてのみ、3)メーカーに圧力をかけることはできても、結果として、メーカーから得た販促費用でさえも消費者に低価格で還元する形となっている・・・。
報告書は、小売もメーカーもともに利益性ある成長を実現するWin-Winの戦略をとらなくてはいけないと指摘している。1987年にウォルマートとP&Gがいわゆる「製販同盟」を結び、これが戦略的協力関係の始まりだといわれている。だが、商品情報を共有することにより、サプライチェーンの無駄を省き店頭での欠品や不良在庫の問題を解決しようとした製販同盟での勝者は大手小売店であり、(大手メーカーも提携先小売店でのシェアの拡大という利益を獲得してはいる)、中小メーカーにとっては負担の増大で終わっていると指摘された。そして、勝者の大手小売店にしても、そこから得た利益はさらなる低価格化を進めるために使われ、自社の利益にはつながっていない。
両者両得のWin-Winの関係構築は、商品中心の情報共有だけではなく、顧客情報も共有することから始まる。
Maracon Associatesは、小売とメーカーがともに利益ある成長を実現するためには、利益ある成長をもたらしてくれる消費者セグメントに重点を置き、そのセグメントが価値あると知覚する商品を提供することだと結論づけている。
ウォルマートは粗利益率の低い低価格品だけでは従来の成長を継続することができないと判断して、高額品も販売するために、顧客調査をして、2億人の顧客を3つのセグメントに分けた。そして、そのうちの1つはNBを選択するセグメントであり、もう一つは価値さえともなえば高額PBを購買してくれるセグメントだと判断した。英国テスコも40~50種類のデータで顧客を10のセグメントに分けた。そのなかには、時間節約のためには高額品を喜んで買うセグメントや、オーガニックとか環境にやさしい商品には高い価格を支払うセグメントが存在していることを発見した。こういったセグメントが望む商品を提供するのが小売の役割であり、そういった商品を開発するのがメーカーの役割だ。もちろん、低価格品しか買えないあるいは買わない顧客セグメントも重要だ。だが、そのセグメントだけに集中していては、売上があがっても利益は薄いまま。持続ある成長は望めない。
長い、長すぎる、しつこい、読みづかれた・・・。スミマセン。お疲れ様でした。
これで、「小売とメーカーのバトル・ロワイアル・シリーズ」は一応終了いたします。次ぎは、サービス・マーケティングについて書きたいと思っております。でも、開始は、もう少し先になると思います。それまで忘れないでくださいね。
引用文献: 1.奥村洋彦「不確実性の分析不可欠」日経新聞6/26/08、2.「ネスレ日本会長兼社長クリス・ジョンソン氏 日本市場は縮まない」日経MJ9/15/08、3.「消費の翻訳 卸の役割」日経MJ8/25/08
参考文献:1. Richard Steele, et.al., Consumer Goods vs. Retail: New Lessons from the Store Wars, Marakon Associates 2003, 2. John H. Fleming, et.a., Manage Your Human Sigma, HBR July- Ausugt 2005, 3. Nancy F. Loehn, Estee Lauder and the Market for Presitige Cosmetics, Harvard Business School 9-801- for Presitige Cosmetics, Harvard Business School 9-801-362
Copyright 2008 by Kazuko Rudy. All rights reserved.